221冊目
『移民の宴 日本に移り住んだ外国人の不思議な食生活』

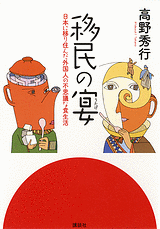
『移民の宴 日本に移り住んだ外国人の不思議な食生活』
著者:高野秀行
発行年月日:2012/11/16
〔はじめに〕
まったく、高野さんにはひでえ目にあわされ続けてきた。死にかけたり、牢屋に入れられそうになったことも一度や二度じゃない。実際、本人はインドから強制送還されて二度と入国できない「罪人」だし、講談社もとんだ人物に賞をやったもんだ。
その人物は、世界征服を目指しているだの、秘密結社構成員や革マル、国際諜報員、革命家、「危険を察知する本能が壊れた人」(作家・宮田珠己氏談)、ジャンキー、三味線芸人ではないか、などとさまざまな憶測を呼んでいる。愛用のマリファナマークの帽子のせいか、吉祥寺近くの自宅から渋谷に行くまで駅を降りるごとに職質を受け、所持品を検査させられ、アヘンを育てた経緯が詳しく書かれた自著『アヘン王国潜入記』(集英社文庫)がバックパックから転げ出てきて、あわや、というところで釈放されたりする。「いつ会ってもわけがわからないというか、形容しがたい残念感と怪しさに包まれている」(作家・内澤旬子氏)ファッションなのだ。だが、その実体は「誰も行かないところへ行き、誰もやらないことをして、それを面白おかしく書く」(高野秀行氏)をモットーにしているだけの作家さん。こんな純粋で損得勘定のない人が悪い人のわけがないのである。だから一緒に旅に出て何が降りかかってきても、まあ、高野さんだし、しょうがねえな、と思わせるのだ。その高野モットーだが、作品になると、一見平易な文章の表層をなぞっただけではあまりにシンプルかつ軽くて、なかなか本質が理解されなかったためなのか、過去に講談社のエッセイ賞、ノンフィクション賞と幾度となく候補にあがっていたにもかかわらず落選続き。このたびの『謎の独立国家ソマリランド』(本の雑誌社)の講談社ノンフィクション賞受賞はうれしいかぎりだ。
〔高野さんとの出会い〕
そもそもの出会いは2001年。吉祥寺の伊勢屋という焼き鳥屋だ。別の出版社にいた大学時代の友人(探検部出身)とまだ日が十分に高いうちから飲んでいたら、たまたま近くの席に昼酒をしている高野さん(やはり探検部のセンパイ)がいたらしい。その友人が気づき、笑いながら立ち上がって僕に紹介してくれたことにはじまる。それがバブル真っ只中の学生時代に貧乏なために栄養失調になっていたという伝説の人物・高野秀行さんであった。
本人が「幸か不幸か顔はもともと間抜けにできている」と謙遜するほど全く警戒感を抱かせない 「カッパっぽい」(本の雑誌社・杉江由次氏)ルックス。「探検家」から想像されるコワモテやハッタリからは最も遠い人物と見て取れた。というか、覇気もなくぼ〜っとした印象であった。今ならそれが高野さんの強力な武器なのだとわかる。でもそれは「能ある鷹は爪を隠す」みたいな話では全然ないのだけど。ともあれ直感的にこの人は信用できると思い「なにか企画をやりませんか〜」と打診し、翌年『西南シルクロードは密林に消える』(講談社)の旅が実現した。
〔高野さんの人物像〕
やがて、ごく一部の物好きな人々のあいだでの熱狂的な反響を置き去りにしたまま絶版になった『西南〜』が7年後、講談社文庫で奇跡の復活を遂げた。そのあたりから「高野さんてどんな人?」と聞かれることが多くなった。そんなとき僕は「体が弱い人」と答えることにしている。辺境地ばかりを取材している作家だから身体が人一倍強いかというと全然そんなことはなく、海外に出かけるといつも二日と置かずに下痢をしている。実は“辺境地における本当の強さ”とはリポビタンDのCMのようにわかりやすいコワモテの姿をとらないし、いわゆる肉体的な勝負の常識からはかけ離れた世界だ。一言では説明しづらいのだけど「語学力」以前の、人への向き合い方だと思う。それは類推する力、共感する感性、憑依させる能力(動物であってもアマゾンの先住民が動物を形態模写するときのような)、なにか魂の本質的な部分の共振といったもの。高野さんを見ていると、本当に強い人とはいわゆるコワモテではないし、すばらしく健康なわけでもないことがわかる。そしてこうしたことは、絶望的な「正論」を振りかざさないことにつながってゆく。
あまたある旅行記の中でも高野さんの作品が「陳腐」に堕していないのは、安易な抒情や感動や共感やエログロに逃げることなく、また、わかりやすい貧困や社会問題、大義名分のジャーナリズムをかさに大上段に深刻ぶって構えることもせず、自分をも相対化して「ダメ人間」とする出発点にある。それが結果として親和性と意外性に富んだ物語の魅力を生んでいる。その魅力は高野さんが予定調和を拒むのではなく“真摯に対すれば世界は予定調和ではない”ということにほかならない。
〔高野さんのこれまでの取り組み〕
この十数年、アメリカののっぺりした文化がキライといいながらも酒がない時には、どんな素朴な民族料理にも決まってコーラを合わせてしまうフレシキブルな高野さんと世界の辺境地を旅してきた。僕が面白いと思うあんなことやこんなことは厳しい高野モットーによって切り捨てられ、ただ外国の旅に出て、呆けたよう普通電車(京成線)で帰ってきました、という「無駄」は数知れない。それでも高野さんは粘り強く『アジア未知動物紀行』『怪獣記』(講談社)といった相変わらず物好きな、というか先鋭的な人々を着実に喜ばせる数々の「高野本」を書き綴ってきた。同調圧力の強い均質的な「日本社会」で、それぞれの人がそれぞれにいいわけがあり、やりたいことがあってもやらないいいわけと、不満をもちながら生きていかざるを得ないなかで、「今の世の中には、絶対に、こういう本が必要なんです。みんながみんな、探検部のメンバーみたいに生きることはできないからこそ」(作家・宮部みゆき氏)、「この本は、いいです。生きる勇気を分けてもらえます」(作家・荻原浩氏)なんていうありがたいエールを送られてもきたわけだ。
高野さんの「誰も行かないところへ行き、誰もやらないことをして、それを面白おかしく書く」モットーは、必然的に「行って・たしかめて・わかる」という『一次情報』しか信用せず、常に直接人と向かい合うスタンスにつながってゆく。
「一人の人間というのはそれ自体が小宇宙だと思う。だから一人の人とじっくり話をするのはーそれが誰であろうとー一冊の本を読んだり、一つの土地を旅するのと同じ醍醐味を感じる」(高野秀行氏)
こうした取材対象に向き合うときの茫洋とした自然体は向きを変えてそのまま読者にも発揮される。難解なことを上から説き伏せたり、権威的な発想を振りかざしたりすることがないのはそうした理由からだなのだ。
〔『移民の宴』について〕
『移民の宴』は月刊『おとなの週末』(講談社)の連載をまとめた高野さんとしては異色な「国内ルポ」だ。異文化経験の豊富な高野さん、ましてや日本国内だから楽勝で取材した、とはならず結果的には海外取材なんかよりもえらく苦労することになった。
取材対象を「日本に暮らすふつうの外国人の食生活」としたものの、いろいろな国のいろいろな事情で日本のさまざまな場所で暮らしている外国人をどこでくくるのか、という問題。さらに国を絞ってアポをとり、話を聞きに行ってもこれまた想定外の理由で「やっぱりごめんなさい」と断られてしまうことも多かったからだ。たとえば、あるときはハーフの生徒を含む外国人率が2/3を超える公立小学校、あるときはうどん屋で働くモンゴル人の音楽家、デンマーク大使館のシェフなど。こうしたひとびとの日本の中の「異文化」の扉をひらいて、さらに多くの豊饒な世界に触れることができなかったのは残念だ。おまけに取材期間中に東日本大震災がおこり、動きの素早いあらかたの外国人が日本から引きあげてしまうという「不幸」にも見舞われた。そんな渦中でもなんとか探しあてた震災後のフィリピン人コミュニティーを訪ねて瓦礫と静けさの支配する南三陸町に取材に向かい、その強さとユーモアに思いがけず明るい気持ちにさせてもらったこともあった。
こう書くとなんだか取材が辛いこと続きだったように思われるかもしれないが、実際は取材を通して新しい知見、珍しくもおいしい食事、想像もしなかった異世界がこんなにも身近に存在していることを知ることで自由な気持ちになり、不思議と救われたような気がする。
それぞれ12章分にまとめられた外国人の食の風景からあらためて無作為に10章ロシア、12章スーダンを振り返ってみると。。。
たとえば日本で祝う(?)12/25日のクリスマスを「アメリカのクリスマス」と呼んでいる人々がいることをどれだけの人が知っているのだろうか。ロシア人が信仰するロシア正教は「西暦」よりも古い「ユリウス暦」を採用していて、キリスト教のより原初の形を受け継いでいるともいわれている。そのクリスマスは1月7日と聞くとお正月の風景がなんだかクラクラと揺らいでゆく。(ロシアンクリスマスを流行らせたら日本はいったいどうなるのだろう)
たとえば日本の野菜として酢の物などでも定着しているオクラだがスーダン人のアブディン氏(盲人の作家)のキッチンのガス台の下から料理に使うための大量のオクラの「乾燥粉末」が出てきた。この「オクラ」がそもそも西アフリカでの呼び名からきていること知ると、「語のもつ意味の厚みは言語システムごとに違う」なんていうソシュールの記号論が中途半端に頭をかすめてゆく。日本食からは想像すらしなかった「オクラ粉末」の異質さに、これまたキッチンの情景が突然変容して見えてくる。(オクラ粉末で新たな日本食もつくれるのでは?)
また、そうした取材の合間のエピソードでも外国人の目を通した異邦感覚が追体験できる。
・日本人に比べて髪が細いロシア人女性が日本の美容室に行くと美容師に経験がないためすっかりボリュームがなくなってしまうという悲劇
・スーダンの石の家から来たアブディン氏が雪深い福井の日本家屋に住んでいたとき、歩くと床がみしみし音がしてほんとに怖かったという恐怖体験
こうした話は異邦感覚としての〈日本〉が予想もしない角度からある種のリアリティーもちながらたちあがってきて、極東の日本人や文化が照射され、日本もまた奇妙な風習を持つ「文化的辺境」にすぎないのだと実感する。 『移民の宴』はそんなネタの宝庫なのである。
〔さいごに〕
高野さんを楽しむもうひとつの方法に、意外にもその著作を通して封印しているがごとき文学性がある。ほんのまれに笑いのベールの向こうから抑制された文学性がほころび出てしまうのだ。
12章ロシアで、戦前に日本で生まれたロシア人女性のリュボフさんが、古き良き時代に折り目正しく生きた日本人が物を大事にするように使い続けている〈昭和の面影を残す古びたガラス器〉を亡くなった高野さんの義父母のそれに重ね合わせて
「かつて私が「白系ロシア人」に感じていたのはファンタジーだった。「本物」を目の当たりにしている今、それはゆるやかに、過ぎ去った昭和へのノスタルジーに変わっていった。」
と結ぶのである。このガラス器はまさに「川べりの道」(作家・鷺沢萠氏の短編)のガラス器のもつ文学性と同質のものだ。
この十余年、アル中、引きこもり、うつ状態だった一人の人間が、こけつまろびつも表現者として階段を駆け上がってゆく姿を目撃した。『移民の宴』ではそんな高野さん自身が、社会学上の「多様性」やキリスト教宗主国的な「寛容」やインド人の「非排他性」などのカテゴリーを超えて、「移民社会」「国際社会」でのありかたを体現している。
(2013.12.15)
![]()
![]()