160冊目
アフタヌーンKC『神戸在住』

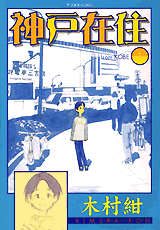
アフタヌーンKC
『神戸在住』(1)〜(10)
著者:木村紺
発行年月日:1999/08/23〜2008/01/23
2011年3月中旬、私は当時在籍していた『週刊現代』で東日本大震災の特集を組むため、岩手県宮古市に来ていた。
カメラマン2人と記者1人、そして私の計4人で、2台の車に分かれて取材に当たっていた。
尋ね人で溢れかえる市役所、机一つ残っていない砂だらけの教室、一面茶褐色に焼け爛れた街並み、そして、悲しむ暇もないほど懸命に働く人々。そこで出会ったあらゆる場面が、未だに自分の中でザワザワと渦巻いている。
夜、彼方に街灯がぽつぽつとだけ見える真っ暗な中で、持参したインスタントラーメンとコーヒーを4人で啜った。その時、ふと思い出したのが、今回挙げた『神戸在住』だった。
このマンガに描かれているのは、神戸にある架空の大学「神戸中央大学校」に通う美術科の女子、辰木桂を中心とした、大学生とその周りの人々の日常生活である。
桂は、勤勉に授業を受けながらも、夜の電車に乗って意味もなくネオンをボーっと眺めてみたり、サークルの部室で非常に低いレートのおいちょかぶをやったりして、日々を過ごす。合間には、中心街にショッピングに行ったり、海水浴に行ったり……そんな他愛もない小話が、ゆるやかに繋がりながら、彼女の生活を彩ってゆく。
自分にも身に覚えがあるエピソードの数々や、神戸弁や大阪弁を話す登場人物たち。あまりのリアリティに、「これは著者の実体験を忠実に描いたものなのでは」とさえ思える。
そして、その話のそこここに、「震災」の影が見え隠れする。
ここで言う「震災」とは、阪神・淡路大震災のことである。
神戸に住むことと、切っては切れない話題だ。
それは例えば、こんな形で現れる。
部室で談笑をしている時、小さな地震が起こると、桂の友人であるタカ美が急に取り乱し始める。泣き叫びながら桂にしがみつくタカ美。揺れが収まると、彼女は真っ青な顔でこう述べる。
〈震災のとき うち 家の下じきになってん……/近所の人たちにガレキの中から引きずり出してもろてんけど……/ほんま うち 死ぬかと思た……〉
その後、部室にいた面々は、敢えて楽しい話をすることで、タカ美の恐怖を和らげようとさりげなく気を遣う。そして、彼女が笑うところで、このシーンは終わる。
このマンガは震災についてだけ描かれたものではない。だが、それだからこそ、「震災が、どのように人々の生活や街に染み込んで行ったか」ということを、雄弁に物語っているように感じられた。
そして、その中のコラムページにあった文章が、記憶の底からむくりと起き上がり、夜の宮古に立つ私の背筋を震わせた。
それは、こんな文章だった。
〈神戸の人はマスコミに強い不信感を抱いている。その言い分はこう。「地震直後にはうるさい位ヘリを飛ばし、長びく避難生活で問題が山積みした頃にはもう、誰一人来なかったから。」林君(『神戸在住』の登場人物で、震災時にボランティアを務めた青年。筆者注)も「ジャーナリズムは必要やけんど」と続ける「その有り様は、もっと問われるべきやった。」〉
「今の自分は、果たしてどうなのだろうか」と、彼方の灯りを見つめながら、先ほどまでの自分の取材を振り返った。
「絶対に被災者に迷惑を掛けない」と、常に意識しながら取材を行っていたが、それを徹底できていたかどうか。そもそも、自分は国民や被災者が本当に求めている取材を行えているのか。新聞でもテレビでもない、雑誌だからこそ伝えられることとは何なのか――。
これから先、震災のことを報じ続けられるかは、自分だけでは分からない。
だが、少なくとも「うるさい」と思われるような取材はすまいと、強く誓った。
震災を伝えようと様々な人が報道を行ってきたが、リアリティのあるマンガで震災を感覚的に伝えようとした作品もあったということを、覚えておきたいと改めて思った。
(2012.07.01)
![]()
![]()