10冊目
文芸文庫『風と光と二十の私と』

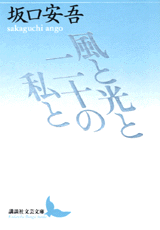
文芸文庫
『風と光と二十の私と』
著者:坂口安吾
発行年月日:1988/10/10
高校生の頃、本を読んだ記憶がほとんどない。村上春樹訳の『キャッチャー・イン・ザ・ライ』が本屋に並んでいた当時、その物語の主人公・ホールデンに影響されたのか、みちのく一人旅と称し、青森から福島付近を、ぷらぷらしていたことは記憶にあるのだけど…その『キャッチャー・イン・ザ・ライ』ですら、ちゃんと読んだかどうか定かではない。唯一、鮮やかに思い出せるのは、坂口安吾の一連の著作のみだ。(講談社文芸文庫から、沢山出ています!)
今回『この1冊!』に取り上げるのは、『風と光と二十の私と』。戦後すぐに 「生きよ堕ちよ、その正当な手順の外に、真に人間を救い得る便利な近道が有りうるだろうか」と「堕落論」を唱えた安吾が、小学校の代用教員を務めていた二十歳の時代を振り返った爽やかな1冊。特に教育関係の仕事をしている方、子どもとの関係が上手くいっていない親御さんに、激しくお薦めしたい1冊である。
『風と光と二十の私と』の中で、注目すべきは、安吾の子どもたちへの眼差し。温かい。決して、「大人と子ども」「教師と生徒」といった単純な二分法だけで、人間を捉えることはしなかった。文中に散りばめられた挿話からも明らかだが、安吾の子どもたちを捉える基本法則は以下のとおり。
「子供のやることには必ず裏側に悲しい意味があるので、決して表面の事柄だけで判断してはいけないものだ」
「子供の胸にひめられている苦悩懊悩は、大人と同様に、むしろそれよりもひたむきに、深刻なのである。その原因が幼稚であるといって、苦悩自体の深さを原因の幼稚さで片付けてはいけない。そういう自責や苦悩の深さは七ツの子供も四十の男も変りのあるものではない」
当時の私は、「秘められた苦悩懊悩は、七ツの子供も四十の男も変りのあるものではない」と、四十の男が言い切ってしまうことに、痺れた。今でも痺れる。やっぱり、安吾はいつ読んでもかっこいい。高校生の頃、本を読んだ記憶がほとんどないのは、私には安吾だけで十分だと判断したせいなのかもしれない。
(2010.11.15)
![]()
![]()